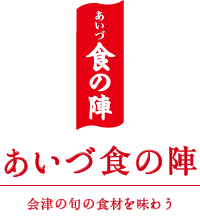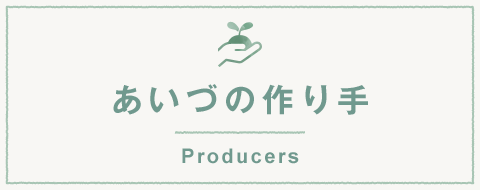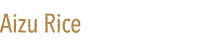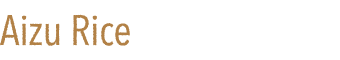料理人と生産者が語る、会津米の魅力
地元の新鮮な食材を活かした料理を提供する「居酒屋舞酒」の店主・鈴木秀幸さん。
そして、家族で専業農家を営み、丹精込めて米づくりを続ける米農家・武田芳仁さん。
「会津米」の魅力やこだわりについて、お二人に語っていただきました。

あいづ西部稲作生産部会 部会長
武田 芳仁 さん
技術や知識を積み重ねる専業農家
サラリーマンを経て実家の農家を継承。平成15年から専業農家となり、耕作面積を広げながら技術や知識を積み重ね、現在に至る。

居酒屋 舞酒 店長
鈴木 秀幸 さん
創業30年の地域密着型のお店
創業30年の「居酒屋舞酒」は、会津米や馬刺し、地鶏料理などを提供。地域密着型のお店として親しまれている。

会津米の魅力を知ってほしい
武田
かつて会津米は、新潟米と並ぶ評価を得て、とても人気がありました。生産者の皆さんは誇りを持って米づくりに励んでいたんです。震災後は風評被害の影響も少な
からずありましたが、「おいしいお米」を届けようと本気で頑張っています。
鈴木
私も子どもの頃から会津米を食べていますが、本当においしいと感じます。地元の方はもちろん、全国の皆さんにも会津米のおいしさを知っていただきたいですね。
武田
会津の田んぼは粘土質の土が多く、水持ちが良いのが特徴です。また昼夜の寒暖差もあるので、旨みのあるお米が育つんですよ。
鈴木
武田さんは、どんなお米を作られているんですか?
武田
現在はコシヒカリ、天のつぶ、ゆうだい21、にじのきらめき、そしてもち米のこがねもちの5種類を栽培しています。それぞれ特徴があって、違ったおいしさを楽しめるんです。
鈴木
昔の会津地方は冷害に苦しむことが多かったと聞きますが、今は温暖化でお米が安定して生産できるのではないでしょうか。
武田
確かに冷害は減りましたが、今は逆に温暖化が課題です。お米は夜にしっかり休むことで育つのですが、最近は熱帯夜が多く、それが難しくなっています。だからこそ、気候に合わせて栽培方法を工夫していかなといけません。
未来へ続く、米づくりの挑戦
鈴木
県外に出かけた時に他の土地のお米を食べると、あらためて会津米のおいしさに気づかされて驚くことがあります。やっぱり会津の風土と生産者の皆さんの努力が詰まったお米だからこそだと思います。
武田
私たちも水の管理や肥料を与えるタイミングなど、日々工夫を重ねています。米づくりは本当に奥が深くて、そこが面白いところでもあります。
鈴木
ご苦労も多いと思います。私も子どもの頃、家の田んぼを手伝ったことがあるので少しわかります。
武田
今は機械化が進み、昔に比べると手作業は減りました。それでも「もっと良い米を」という思いは変わりません。新米の食味を競う「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」への挑戦を続けていきたいと思っています。
鈴木
いいですね!会津米のおいしさを全国に知ってもらえる機会になりますし、評価が高まれば若い生産者が集まって、さらに盛り上がると思います。
武田
そうなれば本当に嬉しいですね。次の世代の方たちと共に、明るい農業の未来を作っていきたいと思います。
炊き立ての幸せを味わう
鈴木
会津の皆さんにも、もっと会津米を食べてもらいたいです。新米が出るたびに「やっぱりおいしいな」と感動します。ご家庭では、炊き立てご飯をシンプルに塩むすびで食べるのがおすすめです。そこに会津野菜の漬物があれば、もう最高ですね。
武田
「食の陣」のような取り組みを通じて、会津米の魅力を知っていただけるのはとてもありがたいです。これからも仲間と協力しながら、おいしいお米を作り続けたいと思います。